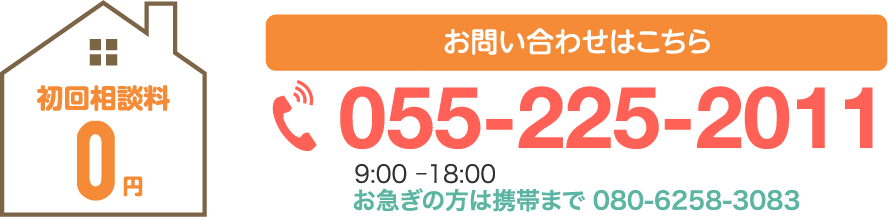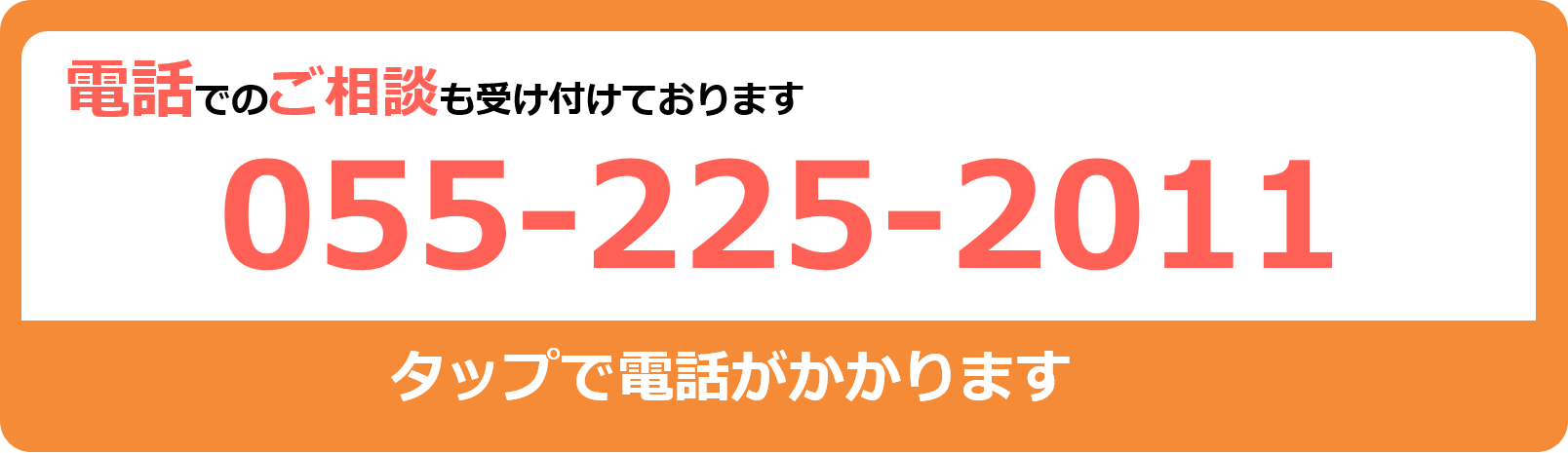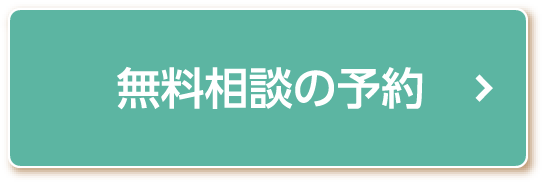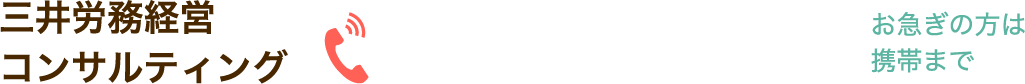心筋梗塞・ステント治療で障害年金はもらえる?受給の条件と申請のコツを専門社労士が徹底解説!

ある日突然襲ってきた胸の痛み、救急搬送、そして心筋梗塞との診断。ステント治療によって一命をとりとめたものの、以前のような生活には戻れず、息切れや強い倦怠感、胸の違和感に悩まされている…。 「退院はしたけれど、元の仕事に戻れるだろうか」「収入が減ってしまい、今後の生活が不安だ」 そのような深刻な悩みを抱えていらっしゃる方は、決して少なくありません。
ステント治療は非常に有効な治療法ですが、それによって心臓の機能が完全に元通りになるわけではありません。心臓の機能が低下し、日常生活や仕事に支障が出ている場合、その経済的な負担を軽減するために「障害年金」という公的な制度が利用できる可能性があります。
「ステントを入れたら、もう元気になったと思われるのでは?」 「自分のような状態で、障害年金の対象になるのだろうか?」
この記事では、障害年金専門の社会保険労務士が、心筋梗塞でステント治療を受けられた方が障害年金を申請するための「基本要件」、認定の鍵となる「検査数値」と「自覚症状」の伝え方、そして具体的な受給事例まで、詳しく解説していきます。 諦めてしまう前に、ご自身の可能性を知るための一歩として、ぜひ最後までお読みください。
Contents
障害年金とは?
現役世代も対象の公的年金
障害年金は、老後に受け取る「老齢年金」と同じ公的な年金制度の一つです。病気やけがが原因で、生活や仕事に支障が生じた場合に、現役世代の方でも受け取ることができます。心筋梗塞のような内部疾患も、もちろん対象となります。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類
障害年金には、心筋梗塞で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって2つの種類があります。
-
障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方が対象です。(自営業、フリーランス、専業主婦(主夫)、20歳以上の学生など)
-
障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。(会社員、公務員など)障害基礎年金に上乗せされる形で支給され、より手厚い保障となっています。
心筋梗塞で障害年金を受給するための3つの基本要件
障害年金を受給するためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
要件1:初診日要件|心筋梗塞で最初に病院にかかった日
「初診日」とは、心筋梗塞の原因となった症状(激しい胸痛など)ではじめて医師の診療を受けた日を指します。心筋梗塞の場合、救急搬送された日や、胸の不調を訴えて循環器内科などを最初に受診した日が初診日となることが一般的です。この初診日によって、受給できる年金の種類が決まります。
要件2:保険料納付要件|年金保険料を納めているか
原則として、初診日の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納めている(または免除されている)ことが必要です。直近1年間に未納がなければ認められる特例もありますので、未納期間があるからとすぐにあきらめず、年金事務所などで確認してみましょう。
要件3:障害状態要件|ステント治療後の認定基準とは?
ここが最も重要なポイントです。「障害認定日」(原則、初診日から1年6ヶ月後の日、または症状が固定した日)の時点で、心筋梗塞後の障害の状態が国の定める等級に該当している必要があります。
ステント治療は血管の詰まりを解消する治療ですが、障害年金の審査では「ステントを入れたかどうか」ではなく、「治療後も、心臓の機能がどの程度低下し、日常生活や労働にどれだけの支障が残っているか」が問われます。
具体的には、以下の項目を総合的に評価して等級が判断されます。
-
自覚症状:少し動いただけでの動悸、息切れ、むくみ、倦怠感など。
-
他覚所見(検査数値など):心電図の異常所見、心エコー検査での心機能の指標(特に左室駆出率:EF値)、胸部X線での心胸郭比(CTR)など。
-
日常生活や労働の制限の程度:以前のように働けない、家事や身の回りのことに支障がある、など。
【等級の目安】
-
1級:常に安静が必要で、身の回りのことがほとんどできない状態。
-
2級:軽い活動でも息切れなどが起こり、家庭内のごく軽い活動や座位を保つことはできるが、それ以上の活動はできない状態。労働により収入を得ることができない。
-
3級(障害厚生年金のみ):日常生活には大きな支障はないが、息切れや倦怠感のため、残業や出張ができないなど、労働に著しい制限がある状態。
ステント治療によって症状が改善したとしても、これらの基準に該当する後遺症が残っていれば、障害年金の対象となる可能性があります。
心筋梗塞の障害年金申請で最も重要なポイント
「治療は成功したのに、体は辛い」という現実を、審査機関に正しく理解してもらうためには、提出する書類の内容がすべてです。
最重要!「診断書」の2つの柱:「検査数値」と「自覚症状」
医師が作成する「診断書(循環器疾患の障害用)」が審査の核となります。ここで重要なのは、客観的な「検査数値」と、ご本人にしか分からない「自覚症状」、この両方をしっかりと記載してもらうことです。
-
検査数値(他覚所見):特に心エコー検査の「左室駆出率(EF値)」は心機能を示す重要な指標です。EF値が50%以下などの異常所見がある場合は、必ず記載してもらう必要があります。
-
自覚症状と日常生活の状況:診断書の「一般状態区分表」や「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」という欄は、ご自身の言葉で伝える症状を医師が記入する部分です。ここが軽く書かれてしまうと、実態が伝わりません。
【医師に実態を伝えるコツ】 診察時間は限られています。口頭だけでは伝えきれない困難さを、具体的なメモにして医師に渡すのが極めて有効です。
(メモの例)
-
「駅の階段を上ると息が切れ、5分休まないと動けない」
-
「以前はできていた、掃除機をかけるなどの家事が、途中で休憩しないとできなくなった」
-
「週に2〜3回、胸に重い圧迫感を感じることがある」
-
「疲れやすくなったため、フルタイム勤務から時短勤務に変えざるを得なかった」
このように具体的な行動と症状を結びつけて伝えることで、医師も診断書に反映しやすくなります。
医師に実態を伝える「申立書」の戦略的な書き方
「病歴・就労状況等申立書」は、ご自身で作成できる唯一の書類です。診断書を補完し、ご自身の言葉で生活の困難さを訴えるための、いわば「プレゼン資料」です。
発症前の生活から、心筋梗塞の発症、治療、そして現在の生活に至るまでをストーリーとして記述します。 「ステント治療で楽になった点」だけでなく、「治療後も残っている症状」や「以前と比べてできなくなったこと」を、仕事面・生活面に分けて具体的に書き出しましょう。診断書の内容と矛盾がないように、一貫性を持たせることが重要です。
もし障害年金が受給できたら?(受給事例)
急性大動脈解離で障害厚生年金3級を受給できたケース
1.病名
急性大動脈解離
●年金種類 障害基礎年金
●等級 3級
●受給額 約797万円
2.相談時の相談者様の状況
相談者:男性(50代)
大動脈に複数のステントを埋め込む手術が行われた関係で、季節の変わり目には体調が悪くなり、普段から労働にも制限が加えられている状態で4年以上経過していた。
3.相談から請求までのサポート
認定日から4年間の治療内容および日常生活・労働における不自由さを詳しく聞き取り、文章化した。
4.結果
障害厚生年金3級を受給し、意欲的に仕事を続けている。
「ステント治療後」の申請こそ専門家(社会保険労務士)に相談するメリット
心筋梗塞・ステント治療後の障害年金申請は、「治療によって改善した」と見なされやすく、ご自身の辛さを客観的な基準に沿って証明するのが難しいケースの一つです。私たち社会保険労務士にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。
-
認定のポイントを熟知:どのような検査数値が重要か、自覚症状をどう表現すれば審査に伝わるかなど、専門的な視点で書類作成をサポートし、認定の可能性を高めます。
-
複雑な手続きの代行:必要書類の収集から申立書の作成、年金事務所とのやり取りまで、時間と手間のかかる手続きをすべて代行します。
-
精神的負担の軽減:「これで伝わるだろうか」という不安やストレスから解放され、ご自身の体調管理に専念していただけます。
-
万が一の不支給にも対応:もし不支給となった場合でも、不服申立(審査請求・再審査請求)まで一貫してサポートします。
まとめ:治療の成功と生活の困難さは別問題です
心筋梗塞に対するステント治療は、命を救う素晴らしい医療です。しかし、治療が成功したことと、その後の生活に困難が残らないことは、必ずしもイコールではありません。
障害年金は、ステント治療後も続く息切れや倦怠感、体力の低下によって、以前と同じように生活や仕事ができなくなった方のための、正当な権利です。
-
心筋梗梗塞・ステント治療後も障害年金の対象となる可能性がある。
-
鍵は「検査数値」と「自覚症状」を具体的に示すこと。
-
日常生活や仕事にどれだけの支障があるかを伝えることが重要。
「自分は対象外かもしれない」と一人で判断せず、まずは専門家である私たち社会保険労務士にご相談ください。あなたのその苦しみが、少しでも和らぐよう、全力でお手伝いさせていただきます。
無料相談・お問い合わせ
心筋梗塞後の生活や仕事、経済的な不安について、一人で抱え込まずにご相談ください。 障害年金に関するご相談は無料です。ご本人様、ご家族様からのご連絡を心よりお待ちしております。