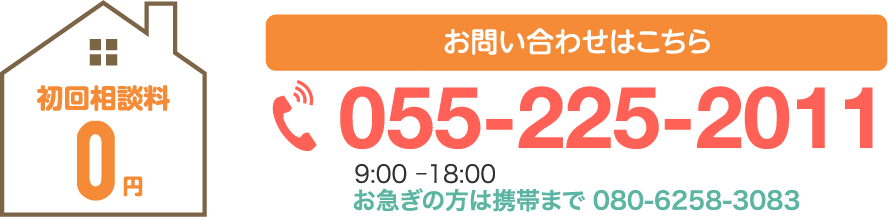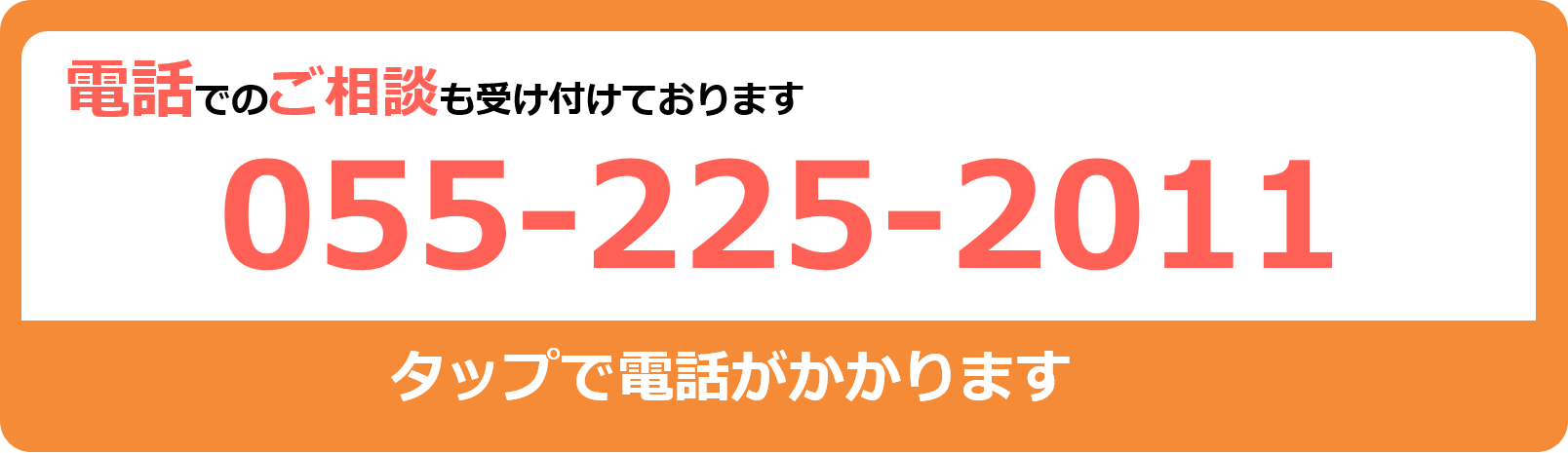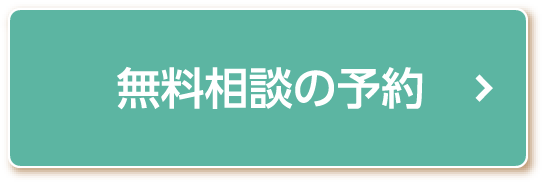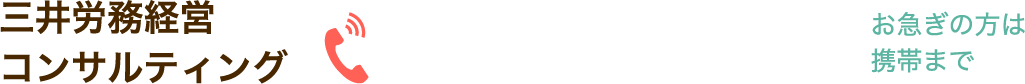【うつ病・精神疾患で悩むあなたへ】障害年金申請をご検討ください|山梨の社労士が徹底解説

「気分の浮き沈みが激しく、仕事が続かない…」
「将来のことを考えると、経済的な不安で眠れない…」
「病気のせいで、当たり前の日常を送ることが難しい…」
精神疾患や発達障害の治療を続けていく中で、このような悩みを抱え、先の見えない不安に押しつぶされそうになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。思うように働けず、治療費や生活費の心配が心の負担となり、療養に専念できない状況は、本当にお辛いことと思います。
そんなあなたの生活を支えるために「障害年金」という公的な制度があることをご存知ですか?
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方々のための、国から支給される年金です。もちろん、うつ病や統合失調症、発達障害といった精神疾患も対象となります。
しかし、近年、障害年金の審査は厳格化しており、特に精神疾患の分野では不支給となるケースが増加傾向にあるという厳しい現実もあります。
「自分一人で手続きするのは難しそう…」
「この状態で、本当に受給できるのだろうか…」
その不安な気持ち、どうか一人で抱え込まないでください。この記事では、障害年金の専門家である社会保険労務士が、制度の基本から、対象となる疾患、申請のポイント、そして皆様からよく寄せられる質問まで、2025年10月現在の最新情報に基づき、分かりやすく解説します。
この記事が、あなたの未来を照らす一筋の光となれば幸いです。
Contents
1. 障害年金の対象となる精神疾患の主な種類
障害年金は、特定の病名だけで受給が決まるわけではありません。その疾患によって、日常生活や仕事にどれだけの支障が生じているかという「障害の状態」が総合的に審査されます。
以下に、対象となる精神疾患の主な例を挙げます。
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
幻覚や妄想、意欲の低下などの症状により、対人関係や身の回りの管理が難しくなるケースが該当します。
気分(感情)障害
うつ病: 抑うつ気分、思考力の低下、不眠、食欲不振などが続き、日常生活に大きな支障をきたしている場合に受給の可能性があります。
双極性障害(躁うつ病): 躁状態とうつ状態を繰り返し、気分の波によって安定した生活や就労が困難な状態が考慮されます。
発達障害
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などが含まれます。対人関係の困難さや、特定の業務への強いこだわり、不注意など、発達特性による二次障害(うつ病など)も含め、社会生活への適応がどれだけ難しいかがポイントになります。
知的障害
日常生活能力や社会生活への適応能力に応じて判断されます。療育手帳の等級とは別に、障害年金の基準で審査されます。
症状性を含む器質性精神障害
高次脳機能障害: 事故による脳外傷や脳血管障害の後遺症として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害などが残り、生活に支障が出ている場合が対象です。
認知症: アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症などで、日常生活に常時介護が必要な状態などが該当します。
てんかん
てんかん発作の頻度や程度、発作がない時でも見られる精神症状などを総合的に評価して判断されます。
精神作用物質使用による精神および行動の障害
アルコールや薬物などの依存症で、精神症状が認められる場合も対象となり得ます。
神経症性障害、ストレス関連障害など
不安障害、適応障害、パニック障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などは、原則として障害年金の対象外とされています。しかし、その症状が長く続き、うつ病や統合失調症と同程度の精神病の病態を示していると医師が判断した場合は、受給できる可能性があります。諦めずにご相談ください。
2. 障害年金を受給するための3つの基本要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
初診日要件 障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が証明できること。精神疾患の場合、どの時点を初診日とするかの判断が難しく、証明に時間がかかるケースが少なくありません。
-
保険料納付要件 初診日の前日において、一定期間以上、国民年金や厚生年金の保険料を納めている(または免除されている)こと。
-
障害状態要件 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後の日)の障害の状態が、国が定める障害等級(1級・2級・3級 ※3級は厚生年金のみ)に該当すること。
これらの要件をご自身で確認し、証明書類を揃えるのは非常に複雑で、大変な作業です。
3. 精神疾患の申請で最も重要な2つの書類
精神疾患の申請において、審査の結果を大きく左右するのが以下の2つの書類です。
-
診断書(精神の障害用) 医師が作成する、最も重要な書類です。特に「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」の項目が、等級判断に直結します。診察時間だけでは伝わりきらない普段の生活の実態(食事、身辺の清潔、金銭管理、対人関係など)を、メモにまとめて医師に渡すなどの工夫が重要です。
-
病歴・就労状況等申立書 ご自身やご家族が作成する唯一の書類です。発症から現在までの経緯、日常生活で困っていること、仕事での支障、症状の波などを具体的に、矛盾なく記載する必要があります。診断書を補完し、ご自身の言葉で審査官に状態を伝えるための大切な書類ですが、体調が優れない中でこれを正確に作成することは、非常に大きな負担となります。
4. よくあるご質問(Q&A)
皆様から特に多く寄せられるご質問にお答えします。
Q1. 働いていると障害年金はもらえませんか?
A1. いいえ、働いているからといって、必ずしも不支給になるわけではありません。 審査では、単に就労しているという事実だけでなく、その「働き方」が重視されます。 例えば、
-
障害者雇用枠で働いている
-
家族や同僚から多くの配慮や援助を受けて、ようやく仕事を続けている
-
短時間勤務で、収入も低い
-
仕事のストレスで、帰宅後は寝たきりのようになってしまう といった状況は、障害の状態が軽いとは判断されず、受給できる可能性は十分にあります。
Q2. 初診日がかなり前で、証明できるか不安です。
A2. 諦めないでください。様々な方法で証明できる可能性があります。 最初の病院にカルテが残っていなくても、お薬手帳、生命保険の告知書、健康診断の記録、第三者の証明など、複数の資料を組み合わせることで初診日を証明できる場合があります。初診日の証明は障害年金申請の入口であり、最もつまずきやすいポイントです。専門家である社労士にご相談いただければ、あらゆる可能性を探ります。
Q3. 精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級は同じですか?
A3. いいえ、必ずしも同じにはなりません。 手帳の制度と障害年金の制度は、根拠となる法律や審査基準が異なります。そのため、「手帳が3級だから、障害年金も3級(または不支給)」と決まるわけではありません。逆に、手帳が3級でも障害年金2級に認定されるケースも、その逆のケースもあります。それぞれ別の制度として申請を考える必要があります。
Q4. 「神経症」「適応障害」と診断されていますが、申請は無理でしょうか?
A4. 原則は対象外ですが、受給できるケースもあります。 前述の通り、神経症圏の疾患は原則として対象外です。しかし、治療を続けても症状が改善せず、日常生活への支障がうつ病などと同程度に重いと判断されれば、受給に至るケースがあります。主治医に診断書作成の可否を相談してみることが第一歩です。判断に迷う場合は、ぜひ一度ご相談ください。
Q5. 家族が本人に代わって相談・申請することはできますか?
A5. はい、可能です。 ご本人は体調が優れず、複雑な手続きを進める気力がない場合も少なくありません。当事務所では、ご家族からのご相談も積極的にお受けしております。ご本人の負担を最小限に抑えながら、ご家族と連携して手続きを進めることができますので、ご安心ください。
5. 専門家(社会保険労務士)に相談するメリット
審査が厳しくなっている今、精神疾患の障害年金申請を専門家である社会保険労務士に依頼するメリットは非常に大きくなっています。
-
負担の軽減: 複雑な書類作成や年金事務所とのやり取りをすべて代行。あなたは安心して治療に専念できます。
-
受給可能性の向上: 最新の審査動向や医学的な観点を踏まえ、あなたの障害の状態が正しく伝わる書類作成を徹底的にサポートします。
-
初診日証明のサポート: 証明が困難なケースでも、あらゆる可能性を探り、粘り強く立証を試みます。
-
精神的な安心感: 専門家が伴走者となることで、「一人ではない」という安心感が得られます。
最後に:希望を諦める前に、まずはご相談ください
精神的な不調を抱えながら、経済的な不安とも戦う日々は、心身ともに大きな負担です。障害年金は、その負担を和らげ、あなたが安心して療養し、自分らしい生活を取り戻すための大切な権利です。
「私なんかが対象になるわけない」
「手続きが面倒だから、もう諦めよう」
そう思ってしまう前に、どうか一度、私たち専門家の声を聞いてください。私たちは、あなたのこれまでのお辛い道のりに真摯に耳を傾け、障害年金受給という未来の可能性を、一緒に見つけ出します。
ご相談は無料です。あなたのその一歩が、明日を変えるかもしれません。